朝日新聞社「ネクストリボン がんとの共生社会を目指して」プレゼン(後半)

わたしは半年抗がん剤を投与しながら会社に通い、その後手術、放射線治療の為1か月お休みをもらいました。
その間に上司のAさんは産休に入ったため、復職後は新しい上司・Bさんと働くことになりました。Bさんと働き始めた頃からはじめた術後5年間続くホルモン治療は、あれほどつらかった抗がん剤とは違う副作用は思った以上に体への負担が大きく、わたしは慢性的に具合が悪い状態でした。
Bさんとの面談の際、Bさんはご自身の「脳腫瘍を患った友人」の話をし始めました。
B「私の友達で若くして脳腫瘍を患った女性がいてね、その子は自分の経験を活かして人の役に立ちたいからって会社を辞めてボランティアのカウンセラーになってた子がいるよ。立派じゃない?……さや香にもそういう道もあることだし」
さ「……(いやいやいや、全然やりたくないんですけど)」
確かに大きい病気を経験をすると、「患者支援」や「社会貢献」に励む方が多いように感じます。それ自体はとても素晴らしいことだと思いますが、わたしはこの会社で働いていて、社会人として成長することを望んでいました。しかしBさんは世の中の「聞いたことのある大病した人の社会生活のイメージ」を前提にわたしと話を進めようとします。
AさんとBさん、二人の上司との働きを通じて、Aさんは目の前の「松さや香個人」として、Bさんは「がん患者の部下」として、向き合っている対象が違うように感じました。
そして、わたし自身もまた自分の中で作った「がん患者」のイメージと思い込みから逃れられずにいました。
告知された当時、とにかく情報が欲しくて本屋に駆け込みました。でも実際に並んでいる書籍たちは、前向きすぎる闘病記や、「愛」や「絆」の素晴らしさを掲げた短歌集や俳句・川柳などばかりがパッケージされていて、「がん患者の実生活」が書かれたものを見つけることができません。
これからがんの治療が始まり、自分が体験するだろう患者としての「生活」をイメージしておきたいのに、世の中にある話の行きつく先は「死」や「病気の恐怖を超えた達観」ばかりが語られていました。
治療の現場で看護師さんやお医者さんにたくさんの症例や実例を見せてもらいながら励ましていただいても、テレビやネットではがんで亡くなった方のニュースや、余命告知された女の子の花嫁姿など「がん=死」を想起させるものばかりが大量放出されていて「お前もそう遠くない将来こうなるんだよ」とテレビのイメージに飲み込まれそうになることに必死に抗っていました。
ご存知の方が大半だとは思いますが「がん患者」の実に様々です。ですがあまりにも社会では「がん患者」としてひとくくりに扱われているように思えます。
もちろんわたし自身、がんと告知された時
「もう働くことなんて難しいのでは?」
「みんなと遊びにも行けないんじゃないか?」
「旅行なんてもってのほかでは?」
「結婚や子どももあきらめなくてはいけないのかしら?」
と、感じおびえていました。
ところが実際は5年の治療を終えた後、旅行どころか37歳で国際線の客室乗務員として空を飛び、子どもこそいませんが38歳で結婚しました。
改めて振り返ると、わたしの治療生活は「がんとの闘い」に加えて「がんのイメージとの闘い」だったように思います。限られた情報の中で自分が作り上げた「がんのイメージ」によって、どれだけ自分自身を追い込んでいたか、今ならよく分かります。
これは決して当事者だけに起こるイメージの弊害でなく周囲の人にも「がんのイメージ」は及びます。
「家族なんだから支えるのが当たり前」
「恋人なんだから受け入れるのが当然」
本当にそうなんでしょうか? 今目の前にある「がん」は病気です。美学や理想、モラルやスピリチュアルで対抗するものではありません。治療にはプロフェッショナルの手が必要になります。そしてご家族の方もまた、人間です。大切な人が病気になったショックは、患者家族の会やピアサポートスタッフの方の力を借りることも必要です。
がんに罹患しても皆さんが皆さん自身のように、皆さんの目の前にいる方も「その方自身」です。テレビや映画の「がん患者」のイメージで接するのではなく、目の前の人が自身のがんをどう感じているのか、そして今何を求めているのか、どうか聞いてあげてください。
自分自身が見聞きしたことで作り出した「がんのイメージ」、テレビや映画、社会で作られている「がんのイメージ」にはまる必要も、押し付ける必要も一切ありません。
そして、がんキャリアの方ご自身の治療経験を心から誇りに思っていただきたいです。今の世の中、自身の立ち行かなさから脱することが出来た、と話しをすると「はいはい、自慢話ですね」と笑われるような風潮があります。でも、わたしは思いっきりその経験を誇りに思ってほしいです。患者の皆さんの存在、そしてその経験を自慢することが、次世代の患者さんへの希望そのものになるからです。その経験を是非、多くの人に共有していただきたいと願ってやみません。
それらはかけがえのない知見になっていくとわたしは信じます。
-
前の記事

朝日新聞社「ネクストリボン がんとの共生社会を目指して」プレゼン(前半) 2018.02.05
-
次の記事
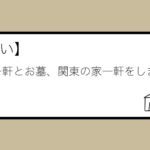
【家じまい①】四国の家一軒とお墓、関東の家一軒をしまいました 2021.06.07